W。帰納法でトッド家族形態論の理論的核心を検証する。
引用
「トッドは、さらに、単なる分類論から歴史的発展論へと論旨を展開している(上図「ユーラシア大陸の主な家族類型」参照)。
すなわち、家族システムの世界分布を説明するため、柳田国男が提唱した「方言周圏論」(図録7720参照)、中尾佐助がナットウのアジア分布(W。面白いことを研究する人がいるものだ。感心する!)を説明するため採用した「エージ・アンド・エリアの仮説」(図録0432参照)と同様の理論展開を行っている。
*****
W。本論から脱線するが面白いので。
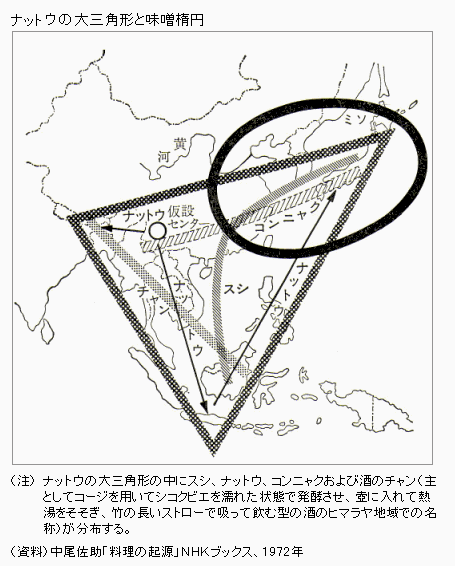
>「>上述のナットウの大三角形とともに味噌楕円が掲げられている。加塩された大豆発酵品である味噌、醤油、タマリなどの一群の加工品の源は中国の華北文化圏とされる。
「豆食品として画期的な発明である豆腐については、ジャワのタフー、ビルマのトーフーと日本のトーフと中国名がひろがっており、中尾によれば、北方遊牧民族が中国にもちこんだ乳加工品である×乳腐の代替品●(乳腐は豆腐の発明より後の時代に生まれている。豆腐に麹をつけ、塩水中で発酵させた中国食品。
醗酵臭と塩味がある。炒め物、煮込み料理などに調味料としてとして中国(華北、あるいは四川)で開発されたものが華僑、留学僧を通じるなどしてアジアに広がったものと推定されている。用いられる以外に、粥に入れて食べる食卓調味料として用いる)
⇒W四川料理の代表格とされているマーボ豆腐は現地では見当たらない日本版四川料理。現地では乳腐を使う。豆腐の新しい食べ方が(乳腐)が中心部に残る、古いものが周辺へ、という事実。日本の豆腐、基本的に無味だが日本人らしいシンプルイズベストな食べ方。
W。下図をよく見ると<寿司>の伝播ルートも記されている。
<握り寿司>~100万都市江戸の労働者職人相手の即席料理。刺身<関西ではおつくり、と昔は言った>も江戸町人相手に天秤担いだ魚屋がその場で調理<古典落語、芝浜>~は江戸発だとおもうが、にぎりめし+加工魚身の<寿司>は本来発酵食品で西日本(関西<京都>)方面の食品。その元の伝播ルートはボルネオということなのか?そう考えると、ある程度納得できる。
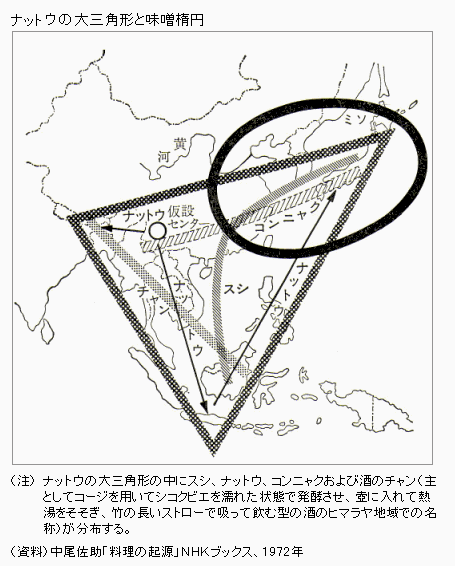
引用 W。本論から脱線するが面白いので。
「納豆、モヤシ、豆腐、味噌・醤油、きな粉など、大豆製品は日本で大いに発達しているが、日本独自の食品ではない。アジアでは大豆製品の利用が広がっている。極東アジアの人々の必要タンパク質の12%が大豆食品から得られているといわれる。」
「日本では、肉類消費が普及する以前は大豆製品が重要な蛋白供給源として食生活の中で重視されていた(図録0280)。現在でも豆腐、納豆、豆乳など日常の食生活になじんだ食品である。全体量で世界2位、1人当たりで世界1位というデータもうなずける。大豆Soybeansという言葉自体、欧米起源ではない。「「ソイ」または「ソヤ」という語は日本語の「醤油」に由来する。
米国の大豆は日本に開国を迫ったペリー提督が日本から持ち帰ってから栽培がはじまり、当初、飼料や干し草として利用され、1911年から搾油がはじまった。大豆粕は高タンパク、低コスト飼料として利用されるようになった。大豆油は当初はせっけん、インキ、セルロイドなどの工業向けだったが、1930年代からマーガリン、食用油として利用がはじまった。大豆はFAO統計では穀物でも豆類でも野菜でもなく油脂作物と分類」。
W。大豆加工食品は今でも日本の家庭料理には欠かせない。昔の大きな農家は大豆を農地の片隅で栽培していた。マメ科の作物は病原菌に耐性があり、育てやすいが、連作不向⇒生育の障害 主にナス科やウリ科、マメ科、アブラナ科などの野菜を連作した場合は、全体的に生育が悪くなる傾向があります。 葉ばかり茂る、新芽が出ない、結実せず収穫量が減る、病気を併発するなどのトラブルが発生し、最終的に枯れるケースも見られます。
>反俗日記は、今の日本は古典的な帝国主義国。モノづくり、ではなく資本輸出と金利で飯を食う国。との結論に達している!
そのように割り切ると日本内外のすべての事象の合理的な説明がつく。下記は未読。
文春新書『老人支配国家 日本の危機』エマニュエル・トッド
ナッ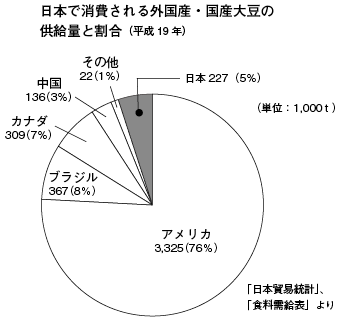 トウ(納豆)はヒマラヤ、中国雲南省から日本までの照葉樹林地帯特有の食品として知られるが、伝来経路は分かっていない。構成樹種として重要なものはシイ、カシ類である。他に、高木層を構成する常緑樹としては、クスノキ科。ツバキ科のツバキ、サザンカ、モッコク、モクレン科のオガタマノキ、ヤマモモ科のヤマモモ、マンサク科、マキ科のイヌマキやナギ。
トウ(納豆)はヒマラヤ、中国雲南省から日本までの照葉樹林地帯特有の食品として知られるが、伝来経路は分かっていない。構成樹種として重要なものはシイ、カシ類である。他に、高木層を構成する常緑樹としては、クスノキ科。ツバキ科のツバキ、サザンカ、モッコク、モクレン科のオガタマノキ、ヤマモモ科のヤマモモ、マンサク科、マキ科のイヌマキやナギ。
現在は開発やスギ、ヒノキなど針葉樹の植林などによる人工林よって、その大部分が失われてしまっており、まとまった面積のものはほとんどない。クスノキ(W.栃木県以南。西日本では公園、園芸樹木として目立つ。生命力が強い。)は東アジア大陸部を原産とする史前帰化植物の可能性が高い。

W。上図はコメ作のルーツを示している。
【弥生時代の稲作とは】日本の米づくりの始まりをわかりやすく解説|リベラルアーツガイド
現在、「朝鮮半島から稲作だけが単体で伝来したのではなく、中国北部の畑作と長江中・下流域の稲作が朝鮮半島で融合し、それが日本にもたらされた」

宮本常一「食生活の構造 (1978年) (シリーズ食文化の発見〈2〉) 」柴田書店、1981年
引用
「明治・大正時代までは食べ物をうまく食べる工夫というよりも腹いっぱい食べることのための工夫が大きかった。しかもそのような工夫に苦しんだのは町に住む人たちではなく、食べ物を作る農民たちであった。作った米の多くは租税としてとられるか、または生活費を得るために売らねばならず、米作をあまり多く行わない畑作地では生活するための経費を得ようとして農業以外の仕事に携わり、自分の家で食べるものは畑で作った雑穀やイモ類が多かったのである。しかもそういう生活が昭和三十年頃(W。1955年~朝鮮戦争1950年⇒1953年~戦争特需によって生産力戦前最高水準に復帰)まで続いた。日本人が米ばかり食べて来たように思っているのはもともとは都会に住む人たちの錯覚であった。」
「町場など移入食料中心の地域を除くと地方の農業生産の特徴に応じて主食の内容は大きく異なっていた。「日本人は昔から米ばかり食べて来たように思っている人が多いけれども、そうではなくてそれぞれの土地で出来たものを食べることが多く、W。地産地消のむしろ雑食であったといってよい。」
W。北海道、東北、の米作率高は幕藩体制のコメ市場化=当該封建軍事貴族の給料化の都合による稲寒冷地品種改良、大規模水田開発と畑作不振によるものと思われる。寒冷地コメ作によって1930年代の世界的天候不良によって飢饉発生(もともと突発的な寒冷気候になる地帯)。
北陸は事情不明(譜代前田藩石高多い)。北海道のその他の食糧生産はジャガイモ。香川の麦はうどん用らしい。河川が無く、降雨量も少なく畑作の麦を<うどん>加工。長野(群馬)辺りの資料があれば面白かった。ソバ作である。

4.戦中にかけての米食の普及
と太平洋戦争の2期が画期だったとしている。
*****
W参考資料。 米騒動発生時点で朝鮮半島は日本への原材料輸出、食料輸出(コメ)のための植民地とされていたので、日本一国の事情では全体像はつかめない。
>大事な点は第1次世界大戦前後の日本は既に原材料(綿花)食料輸入(主に米)国だった、という金融資本主義的色彩を持った帝国主義国という事実。
@古典的帝国主義において農業農民問題は内外の基本矛盾となる。
@今の日本はグローバル資本制下における古典的帝国主義(経済指標の動向基準)であると、割り切って内外事象を眺めていくと腑に落ちる。農業問題は基本問題である。
@このような経済構成の国は現時点で世界に類例がない!日本は特殊な社会経済構成の国である。北朝鮮と分断されている韓国も日本と事情がよく似ている。
産米増殖計画期の日本と朝鮮 近藤郁子
https://www.ritsumei.ac.jp/~yamai/7KISEI/kondoh.pdf
引用
「日本では綿紡績業に牽引されて産業資本主義が確立したのであるが、その原料は日本棉ではなく、インド棉、中国綿、アメリカ棉に依存していたために、原棉を中心とする工業原料が日本の輸入貿易において圧倒的比重を占めていた。
>また、日本は 19世紀以降、恒常的な食糧輸入国となり、
>輸入貿易の中で、食糧は原料に次ぐ重要な位置にあった。
それゆえ、
@朝鮮総督府の農業政策も、併合当初から朝鮮内での食糧自給とともに、工業原料、食糧の輸移出、とりわけ移植のための改良増殖に最大の目的をおいたのである。
*****
1918米騒動(米どころ富山のコメ移出の荷役労働に携わっていた女たちの抗議運動から米騒動は発火)ただし、労働争議は東京をはじめ都市部で頻発しておりその延長線上の女たちの決起であった。幕末、大塩平八郎の大阪蜂起も市中に飢餓による死者が陸続している飢饉下、大阪城代による備蓄米の江戸廻船への怒りだった。
*****
しかし
@1910 年代末においても、依然として降雨に依存する天然水田が大半を占めており日本の優良品種の普及や施肥の増施もそれほどの効果をもたらさず、その他の耕種法の改善も遅々として進展しなかった。これらのことが朝鮮米を日本へ移出するための制約条件になっていた。
そこで 1920 年 12 月から実施した「産米増殖計画」は従来の耕種法の改善だけにとどまらず、大規模な灌漑改善、開墾・干拓などの土地改良業を前面に掲げた政策であった。
朝鮮総督府は「産米増殖計画」を、一方では日本の食糧・米価政策の根本的解決策と位置
づけ、他方ではこの時期に直面した植民地支配体制の危機への対応策=植民地統治維持政策(地主層を支柱化)として位置づけていた。」
引用終わり
「食生活の構造 (1978年) (シリーズ食文化の発見〈2〉) 」柴田書店、1981年)
引用 W。生々しい餌付け?効果ではある。朝鮮からの余剰米に頼って下記のようなコメ選好が生まれた。高度経済成長前期の学校給食は米国余剰小麦製の不味いパンと脱脂粉乳だった。家庭の食生活とマッチしないので無理やり食っていた子供が多かったが、米国風食習慣を刷り込みされたことは間違いない(食料事情の悪い家庭の子供への刷り込み効果は大きかった⇒都会、工業団地の労働力商品へ!。
「大正7(1918)年8月の米価暴騰によって米騒動がおこると「政府は米価を安定させるために外米を輸入した。これを唐米とか南京米といった。
米の味は悪かったけれども白かったので、貧しいものはこれを買って食べた。
>この米が平野に近い山村にも普及して山村民の間で食べられた。このことによって米の味をおぼえ、やがて日本米を買って食べるようになった村が少なくなかった。」
1920年から30年にかけての国勢調査で「山村はいずれも人口の減少が見られた。
なぜ人口が減ったかについては近畿地方山村の役場からアンケートをとったことがあるが、
>その中に「都会へ出ると米が食べられるから」と答えたものがかなりの数にのぼっていた。いったん米の味をおぼえると、もとの雑穀には容易にかえることのできない人も少なくなかったのであろう。」
W.以下のリアリズムを見据える。
「それでもまだ各地域の特色ある雑食が生き残っていたのが、太平洋戦争中に食料統制が行われ、配給米制度が確立するとさらに米食が全国化した。
>「山間の村々などでは戦争のおかげで米が食べられるようになったという声をよく聞いたし、現実にまた私なども山間の村で米食の御馳走にあずかるようになった。(中略)このようにして山間へ米が入り込んでいった。
@つまり日本人全体が米を食べるようになったのは昭和17年頃からだったのである。」(同上)
*****
>日本では室町時代に糸引きナットウがあらわれるので、鉄砲やカボチャとともにポルトガル人の活動に伴ってジャワから導入されたということも考えられるとされる。」
W。なお付け加えると日本で福祉政策が実行されたしたのは第二次世界大戦に至る過程であった。安倍首相「美しい国、日本」で触れられている。元首相の理想はシンガポール。人口減少は不可逆な現象として、危機感はなく少子化対策はない。
W。世界恐慌を受けての高橋是清の財政金融膨張政策は1930年代中盤までは(満州国から戦線拡大、日本経済包囲網まで)徴兵による労働力不足、軍需景気をけん引車として都会の中間層の消費生活を華やかにした。
したがって、暗黒の1930年代のイメージで一括するのは間違い。1936年2,26事件で金融財政膨張政策の出口を模索していた高橋是清は斬殺された。
金融財政膨張政策は今の日本が古典的帝国主義の状態である、とすれば結果は自ずから明らかである。三菱重工の春闘ベースアップ満額回答が報じられている。給与体系、年金その他人件費過多、武器メンテナンス費用過多の自衛隊もこれから景気が良くなる。
台湾、ナショナリズムに依拠する民進党も結局、政権維持のためには対中排外主義に頼るしかない(反俗日記の過去記事で取り上げた。クレオールナショナリズム、公定ナショナリズムまではわかるが俗語ナショナリズムまで培っているのでどうしようもない必ず発火する。現状維持は内外条件から無い。大陸側も今まで通りの経済推移はないのでナショナリズムに頼るしかない。G7の政治経済軍事事情も加速要因である)大陸と島、米国の三者にやりたいようにやらせておけば良い。その間を縫って金儲けをするぐらいに立ち位置にたてないものか。)
*******************************************
時間不足により、場所の記憶に進めなかった。
ページ153
弱い価値観と諸国民の持続
はトッドらしい論法を使っていて特に面白かった。逆も真なりの転倒する一種の弁証法である。
Wはかつて丸山真男の同様の長い論証過程経た日本人の<通史の根底に通じる基底心理の歴史的時空を超えた浮上論~例えばその典型、明治維新の復古と近代化~>を読んだ時、余りにも論証過程が込み入りすぎて投げだした経験があった。
それをトッドは解りやすくさらりとやっている。
>結局、広い視野を持てる民主政相克の場が与えられたものとそうでない者(丸山の記憶の場の持続は日本の戦前と戦後~そうすると欧米基準、日本立ち遅れの講座派的思考に囚われる~)の差。
そしてそういう罠から丸山と違って日本的集団性に埋没するは仕方がないと投げだすのではなく、政治共同幻想から無理なく当たり前の個性を救い出し世界の諸個人は平等である、としている。=民主主義永続革命論(できるわけがないのである)コレに近い政党は社民党だろう。ある意味立派!グローバル資本制に民主政を求め続けるのは個人としても大変だろうと思う。
次のような解りやすい論法、多くの人の身近なリアル感情とその集積、リアルな集団的持続をどのように抽象化できるのだろうか?以下は日本国民にもフランス国民にも共通の場所の記憶(家族親子兄弟、教育、地域、中間組織、テリトリー)の持続である。
「重要なのは多くの個人が弱く有している価値観が、集団レベルでは極めて強く、頑丈で持続的なシステムを生み出し得るということである。
例えば一つに信念が、個々の人間によって濃密に抱かれていない場合でも
あるテリトリーの内部において、長い年月、ときには果てしなく生き続けることがあり得るのだ。
~~~
W。人間大集団の移動があっても、当地の集団的価値観は変わらない理由。
根本的な逆説は
<弱い価値観>という仮説こそが各地の気質の持続性を
いいかえれば、<場所の記憶>という現象を証明してくれる。
@実際にあるテリトリー上の圧倒的多数の歌人の有する価値観が弱ければ、
@これまた相対的に弱い価値観を有していて、
@それを受け入れ側の集団の価値観に取り換える傾向のある傾向のある個人たちが移民として流入してきても、
@結果としてもともとのシステムが希釈されることはない。
>ここでわれわれはホモサピエンスという母胎のの中心心理である<柔軟性>をこの度は<模倣的行動>という概念に結び付けて再び見出している。
社会階層や宗教グループが長く存続するのも集団内の模倣現象によるところが大きくそうした現象は
>強固な信念を再生産するわけではない。
ここでいう価値観は家族に関わるモノとは限らない。生活上の重要な、あるいはとるに足らない、様々な要素に関連するものである。
~~
「欧州単一通貨を図る条約が調印された年から1995年まで
私的な討論の場で個人を相手にする限り単一通貨がばかげたプロジェクトであることを明らかにすることはたやすかったが、
>集団レベルではユーロ導入は不可避だという信念が定着していて、揺るがし得なかった。
>弱い信念が既に十分な広がりを有する集団に担われていて、個人は一時の意見を一変させられても、
>会話を終えて自分が属する社会環境に戻ると同時に元の信念に立ち返ってしまうのだ。
このような現実に気が滅入るけれども
@「弱い個人的価値観」に強い「集団的価値観」が組み合わされる分析モデルには
こころを少し躍らせてきれる含意もある。
@場所の記憶という概念を採用すると
>諸国民夫々の気質が持続していることを理解しつつ
>個人を悪魔化することを、つまり各国の国民一人一人をその国の価値観の執拗な担い手とみなすことを避けれるのだ。
@<場所の記憶>という概念のおかげで
ヒトはドイツ、日本、米国、イギリス、中国、アラブ世界などの文化が持続していることの自明性を受け入れ、
@しかも同時に
各国市民の一人一人を生身の人間でありながら不変の人間の原型であるかのようには1秒たりとも想像しないでいられる。
>個人は自らの所属するグループから離れると、
>たちまち別の方向へ逸れ、もともとの文化から遠ざかるのだ。
>ただその速度に差があることも事実なのでそれも認めよう。
最後までリアリストでいたいものだ。
**********************
**********************
⇒W。膨大な事実を集計し分類すると、法則性の発見に至る。
>そこでトッド家族形態のユーラシア大陸への分類とその歴史的発展過程論と
>柳田の日本列島における「方言周圏論」の法則性(歴史発展過程による移動)が一致した。
第15章 場所の記憶
外婚制共同体家族
ユーラシアの大部分(ロシア、中国、ベトナム、インド北部、ロシア、ベラルーシ
↑バルト三国(注3)東欧(セルビア、ハンガリー)フィンランド
@イタリア・中部トスカナ
