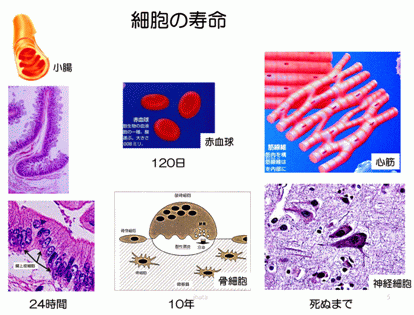修正追加した。一番大切なことを記事にできなかった。
自粛という名の翼賛体制構築に抗する言論人、報道人、表現者の声明
個々人は世界のすべてを認識できるはずはないのに、世界はその全てから成り立っている。
そして世界の、構成主体であり、認識主体である人間も、究極は物質的存在に還元される。


しかし、上記の問題意識の前提を超えて、世界を構成し、認識する側に転倒し、個々人を積極的な行動主体と位置付けると人間的『物質』の叛乱、蜂起にたどり着く。
宇宙史、地球史、生物史、動物史、人類史と『物質』が展開してきた壮大な歴史の果ての只今現在の最先端に存在し続ける『物質』の個々が自らの意思で叛乱し、蜂起し世界に向かい、宇宙史の次元からすると即時に宇宙の無機物に帰っていく。
白井聡「『物質』の蜂起目指して~」はレーニンの唯一の哲学書である「『唯物論と経験批判』(1909年)を素材とした研究論文で、後世の一般的評価では失敗作とされている。リアルに徹するレーニンには哲学は無理だった、機械的な世界観である、レーニンの粗暴性が満開している、哲学的にスターリン主義に通じる問題の書である、などなど評判が悪く、ヨーロッパと日本の高度経済成長以降、この書を正面から取り上げる研究者は、ほとんどいなかった。はっきりいって、今から40年~50年前の時代状況でも読むのに苦痛を伴う書である。もちろん、哲学的素材が満開しすぎて難解である、ということもある。
ソ連崩壊以降、ヨーロッパ、日本(アメリカ論外)で、レーニンを正面から研究対象にする研究者は希少な存在になった。加えて、評判の悪い唯一の哲学書「唯物論と経験論」である。世界的に見て、研究者は白井聡ただ一人ではなかったか。
この点について、特筆すべき面白い事実がある。
その1。レーニンの「唯物論と経験論」は、欠陥の目立つ書ではあるが、今日に通じる哲学的素材が一杯散乱し、考える貴重な素材として、読者の前に投げ出されている。故にもともと、今日的には研究に値する書であったが、研究者たちは気づかなかった。
その2。ではどうして白井は「唯物論と経験論」を正面から研究対象にできたのか?
個人の資質はさておき、今の時代状況が白井の「唯物論と経験論」研究を育んだ。
我々の世代では無理だった。それまで、吸ってきた時代の空気の流れと、経験から捕らわれるものが多すぎて、曇りのない眼で読み込むことができなかった。
そのあとに続く世代も無理だった。知る限り、最新のヨーロッパ政治思想を思想的根拠に論じるのが流行する時代が長く続いた。日本回帰の傾向も深まった。
グローバル金融経済へのすり合せの足りなかった日本に、それが本格的に上陸したのが、小泉政権時代の2000年であった。
2015/2/4(水) 午後 7:30
「2005年ホリエモンのニッポン放送(フジテレビ株の多くを所有)買収騒動のとき、「- 株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社デニーズジャパンの3社が株式移転により3社の持株会社として設立。」
この同じ年に我が阪神タイガースの親会社、阪神電鉄の村上ファンドによるマスコミ宣伝を利用した派手な買収騒動が突発する。この年阪神タイガースはセリーグ優勝を果たしたが、親会社の去就が混とんとして日本シリーズの時点では野球どころではなく、4連敗してしまった。
グローバル資本制の進展、そのものが、対抗物として<『物質』の蜂起をめざして>――レーニン、「力」の思想」をうみだした。
先回りすると、「永続敗戦論~戦後日本の核心~」は、グローバル資本制の時代趨勢が生み出した、といえる。
『「物質」の蜂起をめざして――レーニン、「力」の思想』は本のタイトルであると同時に、研究対象を白井流に再構成した総括と見る。レーニンの政治思想のよって立つ根拠を突き詰めていくと、そういう次元に到達してしまうのである。
そういう白井の再構成力のありようは、「永続敗戦論~戦後日本の核心」というタイトルに見事に再現されている。白井は戦後日本を再構成し、永続敗戦と総括したのだ。
その4。ルカーチという政治思想家がいる。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%B8
一般に知られている代表作は『歴史と階級意識』(Geschichte und Klassenbewusstsein;1923年
前者は書店に並んでいたとき読んだ記憶があるが、ピンとこなかった。その方面では日本の研究の方が進んでいると思ったからだ。
ところが、何とはなしに直近で読む機会があった。
つまり、ロシアで革命は起こりうるとリアルタイムに念頭に置いて、すべての活動をそこに集約して展開していた。そうすると<党>は自分たちの政治思想を具現化し、大衆に伝播する決して手放してはならない存在になり、後は政治思想の強化(「唯物論と経験論」もその一環で書かれている)と政治技術の問題になる。
ルカーチの証明は至って現実的である。
次のような文脈から、レーニンの<革命の現実性>説明していく。
長々と執拗に書き連ねるが、白井聡と時代状況という、今回の記事の一つのテーマの視点から意味深い作業である。しかしいかにも長すぎる
要約を先に挙げる。
>日本の今の感覚でいえば、
バブル完全崩壊後の1996年。→1月11日 - 橋本龍太郎内閣発足。2月16日 - 菅直人厚相、薬害エイズ事件で血友病患者に直接謝罪。4月24日 - オウム真理教(現:Aleph)元教祖の麻原彰晃(松本智津夫)被告の初公判が東京地裁で開かれる。
レーニンの政治思想が骨格がはっきりした「何をなすべきか?」1902年はパリコミューン1871年の31年後である。レーニ31才のときである。
その4.従って。レーニンにとって、パリコミューンは<革命の現実性>をリアルに持続できる象徴であった。
増して日露戦争、まっただ中の1905年ペテルブルグの蜂起があった。
くわえて、ロシアの革命運動は圧迫され続けながらも、党派にかかわらず、持続していた。
大衆運動の自然発生性を根強いものがあったがゆえに、1902年「経済主義批判を主な目的として『何をなすべきか?』を書いた。労働者の自然成長的な経済闘争(W、今で言いう賃上げ条件闘争とは色合いが違う)はそれ自体としてはブルジョア・イデオロギーを超えない、と指摘し、社会主義を目指す政治闘争を主張した」。
レーニンはものすごい粘着力を持って、<革命>に固執したが、気持ちの持ちようで、革命はリアルなものであった。レーニンは夢想家でも何でもなく、リアリストである。ロシアの政治と人民動きによって1917年の事態を迎えたのである。
結論。時代が人を動かし人を作る。グローバル金融経済は必ず、何らかの形をとって対抗物を生み出し続ける。
それを適切にどうくみ取るかが最大の課題である。
日本の政治の一つの大きな欠陥は、民衆側に自然発生性、自然成長性が乏しいことである。民衆側に自然発生性、自然成長性の実存しない状態において、レーニンのごとく、その否定的側面をあげつらう政治思想はこの日本では本質的に悪い作用を及ぼすことが多い。むしろ、そういったものを政治主体の側から、積極的に作り出さなければならいのだから。
政治主体の側はこの点に大きな勘違いがある。認識の深化、大衆啓蒙、あるいは党の先進性への大衆の吸収にすり替えている。
したがって、大衆規模の集団的政治経験に乏しくがゆえに、政治に対する現実性が庶民の間に欠如し続ける。選挙の際に1票を投じることは、敢えて言えば、政治行動の一部ではあるが、大衆規模の集団的政治経験では有り得ない。国民規模の政治の自然成長をもたらすものでない。
だから、容易に逆方向に大きく振れていく。
政治経験の乏しいところに、リアルでインパクトのある政治思想は育まれるはずがない。
込み入った日米政治構造の語り合う対談の動画の最後の参加者の質問は、自分でもできないような高度な質問が続いた。
その中の一人は、今度の選挙で、今の政治の現状を見ると、どの党に投票したらいいのかと問うた。その人も高度な質問ができる部類と見たが、あきれ果てた。最大の愚問である。
あらゆる場合を想定して考えて、一人で結論を出す問題だからだ。識者に尋ねることでは全くない。
対談者は厳しくたしなめるべきだった。それを自民党以外なら~と答えている。このヒトの話は何度聞いても尾の白いが、ラッキョの皮むき、の象徴である。
Uさんというエコノミスト兼、政治評論家は国政選挙の度ごとに、ブログの閲覧者に向けて、政治恫喝めい言論を展開し、投票誘導を行っている。そういった指図に、激しい嫌悪を感じる。自民党に投票しようが公明党だろうがそれはその人の自由である。このハンドルに例えるとアソビがないから、肝心な時に政治判断を誤るのである。
引用、
YAHOO知恵袋
「ベストアンサーに選ばれた回答
W。明快である。
*<市民革命>の現実性をスポイルされた日本において、白井の作業は困難で、貴重である。
それほどの大きなハードルを越えた考察だった。
*しかし、日本の最先端の研究は、育む力がもともとがあったのである。
そう言い意味で彼は日本の社会思想研究の王道を歩む研究者と捉えている。アンチの次元を超えて統一し合体できる立場を獲得したのである。
「永続敗戦論~戦後日本の核心~」において、一端は肯定的に取り上げた、江藤淳を否定し、福田 恆存(ふくだ つねあり)を否定しなかったのは、その意味でよくわかる。福田の政治思想はは統合すべき存在である。
「パリ・コミューンパリ市の自治市会(革命自治体)のことであるが、ここでは国防政府のプロイセンとの和平交渉に反対し、同時期にフランス各地で蜂起したコミューン(la Commune)のうち普仏戦争後の1871年3月26日に、史上初の「プロレタリアート独裁」(マルクス)による自治政府を宣言したパリのコミューン(la Commune de Paris 1871)
「国民衛兵中央委員会の一部に第一インターナショナルが参加していたことから、カール・マルクスはコミューン崩壊の2日後、『フランスの内乱』を執筆し、コミューン戦士の名誉を擁護するとともに、コミューンの事業からプロレタリア革命理論を抽出した。この著作の中でマルクスはコミューンを労働者階級のための国家と規定し、共産主義革命におけるプロレタリア独裁の歴史的必然性を説いた。
W。レーニンの経歴を見ていくと、<革命の現実性>とは文字通りのものであって、革命主義者が無理やり抱く妄想ではないとわかる。
パリコミューン→1871年。
レーニン(1870年ー1924年)
青年時代
1886年1月に敬愛する父イリヤ・ウリヤノフが脳出血で倒れて亡くなり、翌年にはペテルブルク大学理学部に在籍していた兄のアレクサンドル・ウリヤノフが、ロシア皇帝アレクサンドル3世の暗殺計画に加わった容疑で絞首刑にされた。
、カザン大学から退学処分を受けた。
ウリヤノフ兄弟は帝国政府から「テロリストの兄弟」として危険視され、常に秘密警察から監視される日々を送る事になった。レーニンは監視の中で暴動を控えて「資本論」などカール・マルクスの著作を読み耽り、思想研究に没頭して理論面での活動を志し始めた。
1892年第一法学士の称号を与えられる。
政治家へ
1895年労働者階級解放闘争ペテルブルク同盟を結成するが、逮捕と投獄。
1897年シベリア流刑。
ロシア社会民主労働党の再建と分裂
1900年経済主義に反対して政治闘争を重視する活動家とともに政治新聞『イスクラ』を創刊
1902年経済主義批判を主な目的として『何をなすべきか?』を書いた。労働者の自然成長的な経済闘争はそれ自体としてはブルジョア・イデオロギーを超えない、と指摘し、社会主義を目指す政治闘争を主張したものである。 ↓ ↓
1903年再建されたばかりの党はボリシェヴィキ(多数派)とメンシェヴィキ(少数派)という二つの分派に分かれた。「イスクラ」編集局の6名のうち、レーニン以外の5名はメンシェヴィキへ移ったため、レーニンはボリシェヴィキの突出した指導者となった
第一革命と労農民主独裁論
『唯物論と経験批判』(1909年) 『哲学ノート』(1913年) 『帝国主義論』(1916年) 「四月テーゼ」ロシア語及び英訳(1917年4月) 『国家と革命』(1917年8月)